インターバル歩行のすゝめ①~③で、お散歩の目的(①運動②精神的に満たされる③社会化効果④トレーニング効果)を達成するには、「ただ1時間歩くだけではその効果は低いですよ!」ということを述べてきました。
そこで、お勧めしたいのが『インターバル速歩』。
これは、歩行の4つの目的すべてに効果のある、嬉しすぎる方法で必見です!
インターバル速歩とは?
インターバル速歩とは、❝速足❞と❝ゆっくり❞を3分ずつ交互に繰り返して歩く方法で、人の体力アップに大きな効果を発揮する歩行として紹介されているものです(詳しくは『ウォーキングの科学』をご参照ください)。
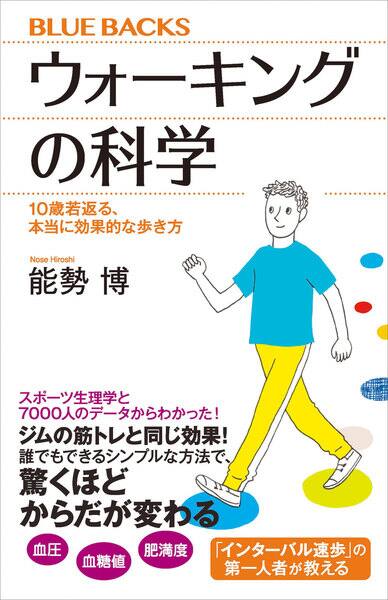
❝速足❞は人の最大酸素量の70%程度のスピードで歩くことが推奨されています。
速歩の時は、意識的に腕を振って大股で歩きますが、この状態で3分歩いたら、私は軽く息が上がり、じわっと汗が出るような歩行スピードです。
❝ゆっくり❞は最大酸素量の40%程度なので、普通よりもやや遅いスピード、速歩で上がった息を整えるのにちょうどよいスピードです。
「普通に歩いた人」と『インターバル速歩』でをした人を比較したところ、「普通に歩いた人」は1万歩歩いていても体力の向上が見られませんでしたが、『インターバル速歩』は8千歩でも体力の向上が認められ、年齢にすると10歳若返ったくらいの効果であったという結果となりました。
歩く距離ではなくて、質が大切ということです。
インターバル速歩と犬の散歩
これは犬との歩行においても効果は抜群!
犬のお散歩の目的に合わせてみると
①運動効果
1時間歩いていたパピーが内臓脂肪がついていたというエピソードをご紹介した通り、犬においても運動効果を求めるなら、ただ歩くのではなく、少し負荷のかかる歩行スピードが必要です。
犬の歩き方で言うと(犬の歩く種類は以下の通り)、②速足~③駆け足の歩き方のスピードです。
つまり、インターバル速歩は犬の速足を促すことになりますので、体力的にも満たされることになるでしょう。
(以下にインターバル速歩の動画も挙げていますのでご確認ください)
①並足(なみあし/ウォーク/人が普通に歩くときのスピード)
ゆっくり歩く時の足の運びで4本の足を1本ずつ動かす歩き方です。重心移動が少なくてあまり胴体を揺らさずに歩くので疲れません。人が普通のスピードで歩いた時のスピード。
②速足(はやあし/トロット/人の早歩きのスピード)
斜め向かいの足同士2本がペアとなって一緒に動きます。並足よりも歩幅が広く、やや早くスタスタと歩く歩き方です。
③駆け足(かけあし/キャンター/自転車のスピード)
体をリズミカルに上下しながら1本ずつ足を地面につけて、蹴るようにして元気に走ります。自転車のスピード。
④襲歩(しゅうほ/ギャロップ/世界最速の男のスピード)
体をバネのように思いっきり伸び縮みさせて走る犬の全速力のスピードです。足の動かし方は駆け足と同じですが、一瞬4本足全部が空中に浮いている状態があります。体力をとても消耗するため持続することはできません。
②精神的に満たされる
ゆっくり歩くとコルチゾールが下がることはわかっていますが、ただゆっくりと歩くよりも、速歩きをしてコルチゾールをいったん上げてからゆっくり歩いた方が、よりリラックスする効果が高いのだそうです。
これはインターバル速歩そのままですが、実際にインターバル速歩を実施した人は気分の向上にも効果があることが証明されています。
③社会化効果
社会化のためには、歩行経験は大切ですが、人とのコンタクトを維持した状態で経験していくとより効果的。
人とコンタクトを維持する上で有効なのがインターバル速歩です。
人のペースで速足とゆっくりを繰り返すことに犬が合わせることで、自然とコンタクトをとった歩きになります。
④トレーニングとして
トレーニング効果を高めるためには人と安定したコンタクトを維持していることが大切です。
速い歩きと遅い歩きを繰り返すことで、歩く上での主導権が人になります。
人の組織においても、リーダーに対して同調行動がみられるようになりますが、インターバル速歩で人に同調行動を求めることで、人がリーダーシップを発揮することができます(リーダーウォーク)。
まだまだあるぞ!
『ウォーキングの科学』では、インターバル速歩の効果は他にも紹介されていて以下のようなものがあります。
〇睡眠の質を上げる
〇認知機能の改善につながる
実際に犬でも、歩行スピードが遅い犬と認知症に相関関係があるという研究結果もあり、速く歩くことを意図的行うインターバル速歩は、犬の認知機能低下を抑止することにも効果があるでしょう。
インターバル速歩は人にも犬にもいいことだらけ!
是非お試しあれ!(^_-)-☆



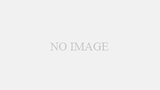
コメント